 トップページ
トップページ ×
×
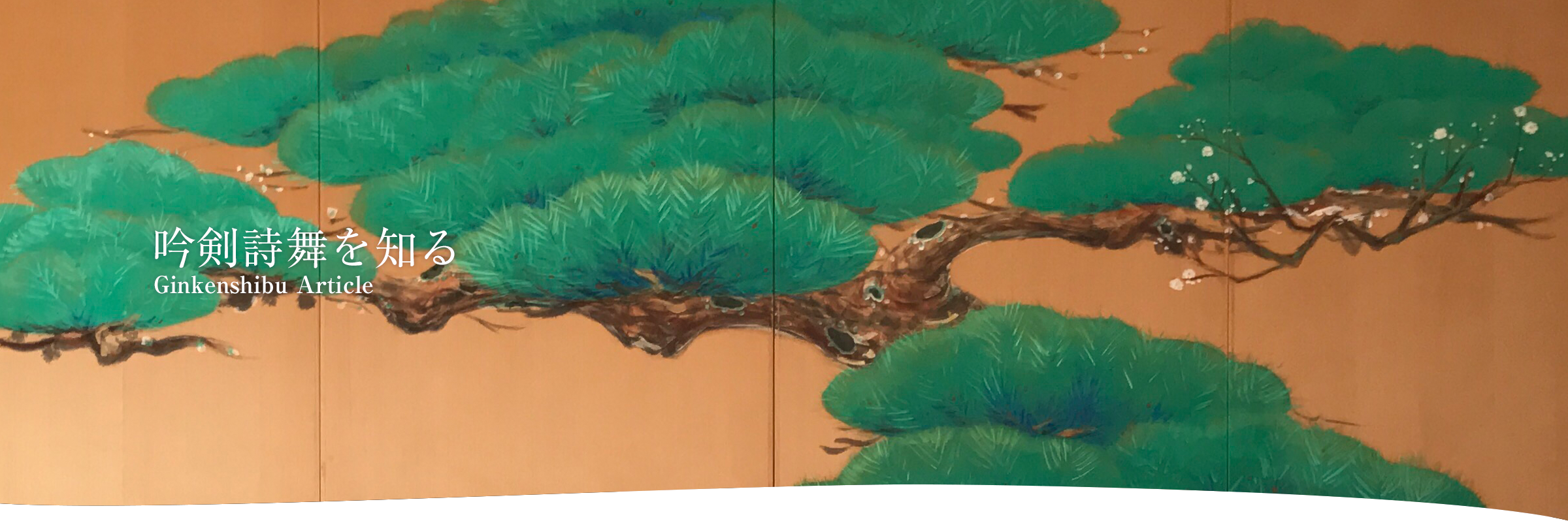

吉田松陰「辞世」
吉田松陰は、安政元年(一八五四)、浦賀に来港した米艦に乗りこもうとして拒まれ、自首して江戸伝馬町の獄に下りました。のち故郷の萩に帰って野山獄に投ぜられ、出獄すると実家に幽閉の身となり、この間、松下村塾を主宰して後の維新に活躍する多くの子弟を教育しました。
安政五年(一八五八)井伊直弼が勅許を持たず日米通商条約に調印して天下が騒然となると、幕府は真部詮勝を上洛させて志士を捕縛しようとします。松陰はその暗殺を企てたため、藩によって再び幽閉され、十二月獄に投ぜられ、翌六年五月、藩命によって江戸に護送されます。そして、十月二十七日、小塚原で斬首。享年三十歳でした。
この「辞世」は、安政六年十月二十日、刑死七日前に、獄中から郷里に送ったもので、みずから朗々と吟じたものを筆記させたといいます。また評定場で死罪を申し渡され、くぐり戸から出た直後に朗々と吟じられたともいいます。評定場の役人や護送役人は松陰の漢詩に聞き入り、朗詠が終わると我に返り、松陰を籠に乗せて伝馬町の獄まで連れて行ったと記録されています。
松陰は「志を立てる」こと、「至誠を貫く」ことを大切にしていました。伝馬町の獄で高杉晋作に手紙を書いています。「死は好むべきにもあらず、また憎むべきにもあらず」と。また「世に、身生きて、心死する者あり。身亡びて魂存する者あり。心死すれば生くるも益なし。魂存すれば亡ぶも損なきなり」とも言います。漢詩にはこの思いが詠われています。
吾今爲國死[吾今国の為に死す]
死不負君親[死して君親に負かず]
悠悠天地事[悠悠たり天地の事]
鑑照在明神[鑑照明神に在り]
〈いま私は国のために命を捨てようとしている。(私はこれまで、より良い国を築こうと志を立て、至誠を貫いてきた。だから志半ばで)処刑されても、天子や両親にそむくことは何もない。悠々として永遠な天地の(間の様々な人間の歴史の中で、後世に残る)事は、(志を立て至誠を貫く魂であり、この魂こそは)神明が照覧されているものである。(魂は天地とともに永遠に残る。それ故、私は何も後悔することなく、死につくことができる)。〉
「負」は恩に違い徳を忘れること。「君」は世を治める天子。「鑑照」はうつして照らす。明らかに見分けることを言います。「明神」はすべてを見通す神。
衝撃的な詠い出しです。刑死することのない人、刑死する人であっても信念のない人には言えません。私情をはさむことなく、より良い国を作るために命を捧げた人にして初めて言えることです。二句目は志を実現するために至誠を貫いてきたので、死んでも君主や両親にそむくことなく、愧じることはないと言います。
松陰は、しかし、孝を大切にする人でもあり、刑に臨んで次のように詠っています。
親思ふ心にまさる親心けふのおとづれ何と聞くらん
母親は気丈な方で、息子の刑死を知らされても言動は普段とかわらなかったといいます。
後半の「悠悠たる天地」は、永遠に続く天地です。松陰は、死んでも不朽の見込みがあるならいつでも死んでよく、生きて大業の見込みがあるならいつまでも生きるべきだ、生死は問題ではない、とも言っています。志を立て、わが身を捧げて至誠を貫く魂こそは神明によって照覧され、天地とともに永遠に存在すると考えていました。だから、平然と死につくことができたのです。
刑の執行のとき、松陰は役人に「ご苦労様」と挨拶をして端坐し、泰然として首を打たれたといいます。辞世の歌も伝わっています。
身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも留め置かまし大和魂
