 トップページ
トップページ ×
×
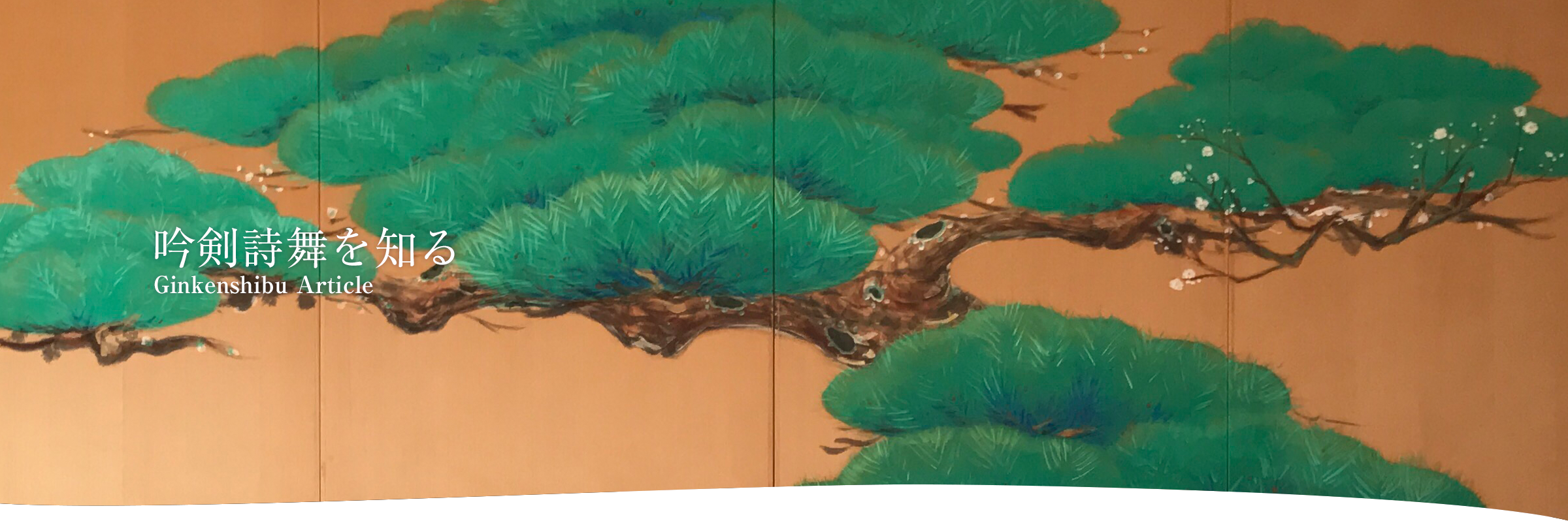
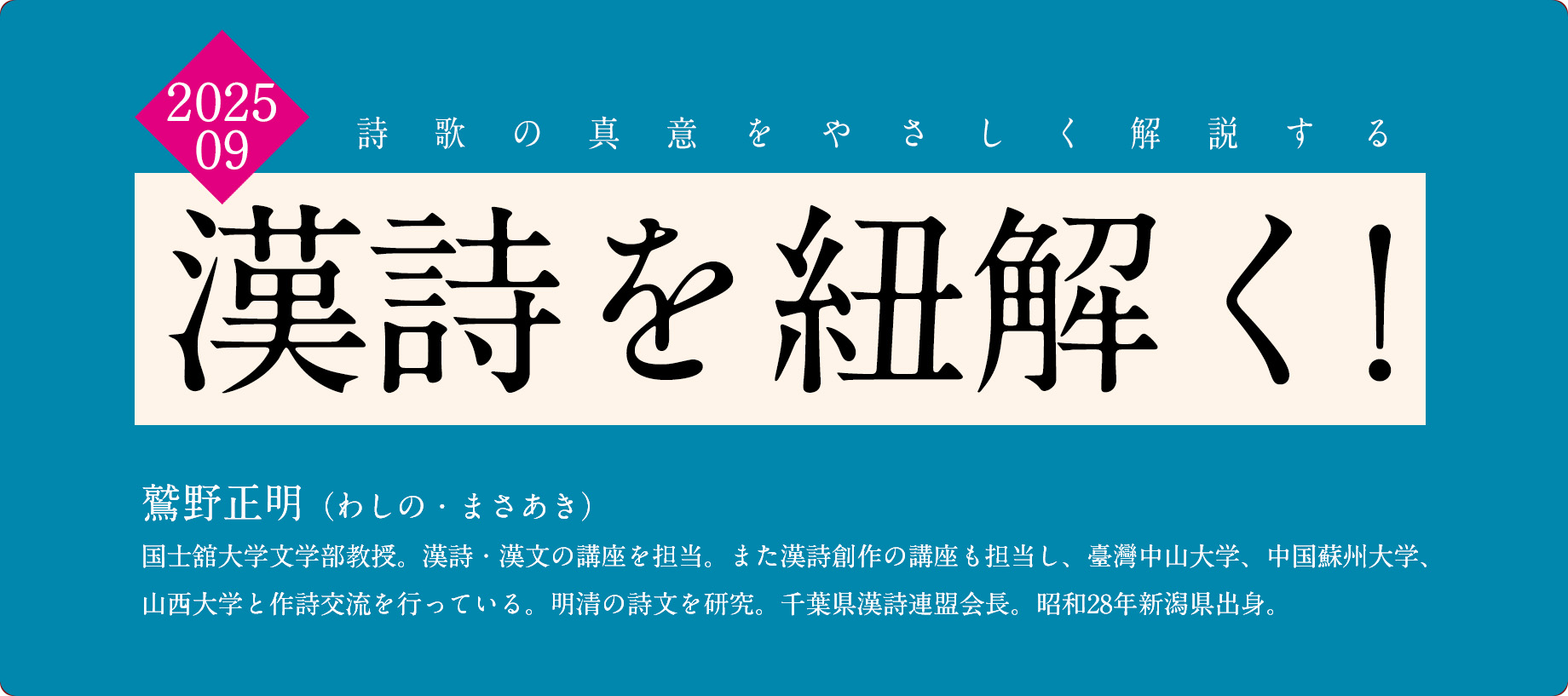
月田蒙斎「暁に発す」
訓読は古典文法にしたがう古い読み方ですから、今日の言い方と異なる場合があります。例えば「大蛇が道に横たわっているのを驚いた」と言うと、今日では間違いということになります。しかし漢文訓読は「忽ち」を伴って「忽ち驚く~を」と言うことができます。「忽ち」は、ふと、急に、の意です。月田蒙斎の「暁に発す」に「を驚く」の読みが出てきます。
殘月滴露濕人袂[残月の滴露人の袂を湿す]
曉風吹髪覺秋冷[暁風髪を吹いて秋冷を覚ゆ]
忽驚大蛇當路橫[忽ち驚く大蛇の路に当って橫たわるを]
抜剱欲斬老松影[剣を抜いて斬らんと欲すれば老松の影]
この「を」の読み方は江戸時代の版本を紐解いてみるといくつか見出せます。例えば六如の「夏日」。
午睡不知雨入樓[午睡知らず雨楼に入るを]
忽驚懸瀑濺簷頭[忽ち驚く懸瀑の簷頭に濺ぐを]
須臾雲散簾櫳敞[須臾に雲散じて簾櫳敞なり]
斜日鳴蟬一院秋[斜日鳴蟬一院の秋]
承句「濺」の送り仮名は「クヲ」となっています。版本では濁点は表記しません。因に転句「散」の送り仮名は「メ」となっていますが、これは「シテ」の省略形です。また「敞」の送り仮名は「カ也」です。「也」は崩し字になっています。
前半は、昼寝をしていると楼の中に雨が降りこんできたので、びっくりして目が覚め、外を見ると簷に滝(懸瀑)のような雨が濺いでいた、ということです。「簷頭に濺」いでいたのは雨であって滝ではありません。滝のような土砂降りの通り雨だったので「忽ち驚いた」のです。内容を踏まえて「忽ち驚く懸瀑の簷頭に濺ぐかと」と読むこともできます。もし実際に滝が濺いでいたなら「忽ち驚く懸瀑の簷頭に濺ぐに」と読むことになるでしょう。
「を驚く」の例をもう一つ。柏木如亭の「三月二十三日風日初めて美なり」の第二首。転句「忽驚茆屋有人住」は「忽ち驚く茆屋人の住する有るを」となっています。ふと、隠者が住む茅葺の家があるように思った、秦の始皇帝の勅命によって遣わされた人の子孫が住んでいるなら訪ねてみたい、と。花の香りと夕陽の美しい光に、ふと古代のロマンを感じたのです。これも「忽ち驚く~かと」と読むことができます。
月田蒙斎の「暁に発す」に戻ると、大蛇かと思ったのは松の影です。もし実際に蛇が横たわっていたなら「忽ち驚く大蛇の路に当って橫たわるに」となります。が、錯覚だったので「忽ち驚く~を」と読んでいるのです。これも「忽ち驚く~かと」と読むことができます。
漢文訓読の「~を驚く」は、そのまま現代日本語に置き換えて「大蛇が横たわっているのを驚いた」と訳すとおかしなことになります。そこで当振興会編の『漢詩集』(続絶句編・一五一頁)では〈ふと見れば、巨大な蛇がゆくての道をさえぎるように横たわっているではないか……よくよく見ればそれは年を経た松の影であった〉と、内容を踏まえて分かりやすく訳してあります。
ところで、大蛇がいる、となぜ驚いたのでしょうか。それは、蛇が出そうな不気味な雰囲気のなかで、樹の枝の影がくっきりと地面に落ち、しかも動いていたからです。詩の前半で、月明かりと風を詠っているのに着目してください。そして露で袂がぬれ、冷たい風で首筋がぞくっとした、と詠っています。詩語の選択と連絡、全体の構成、とても参考になります。

