 トップページ
トップページ ×
×
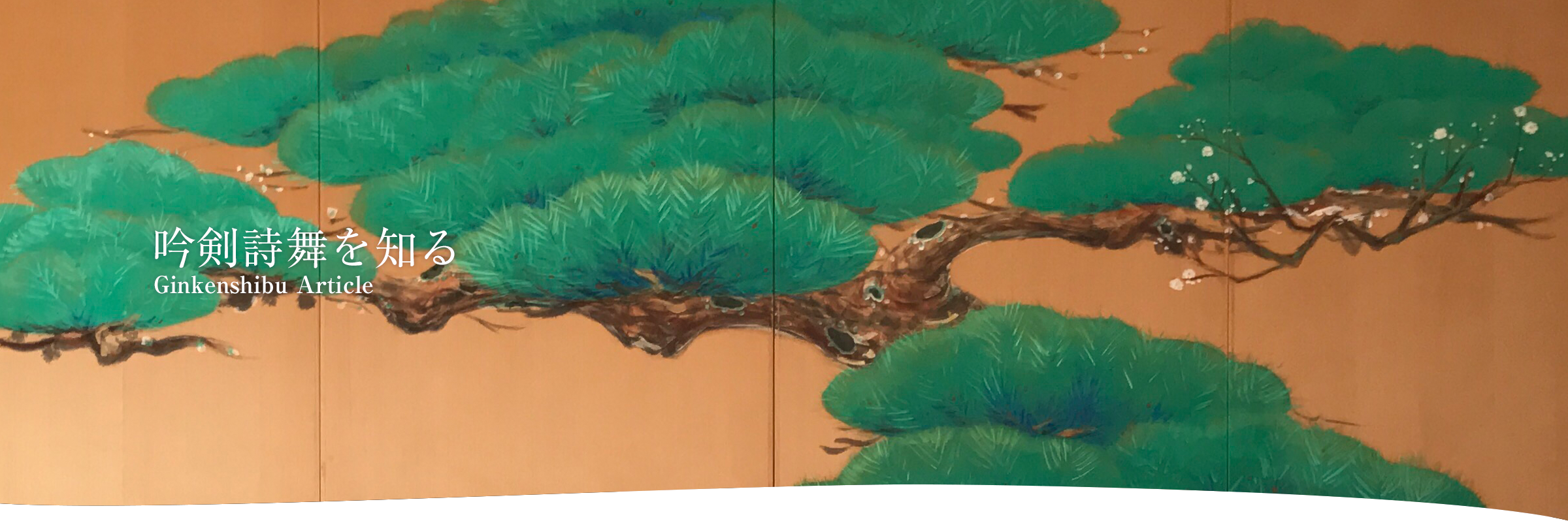
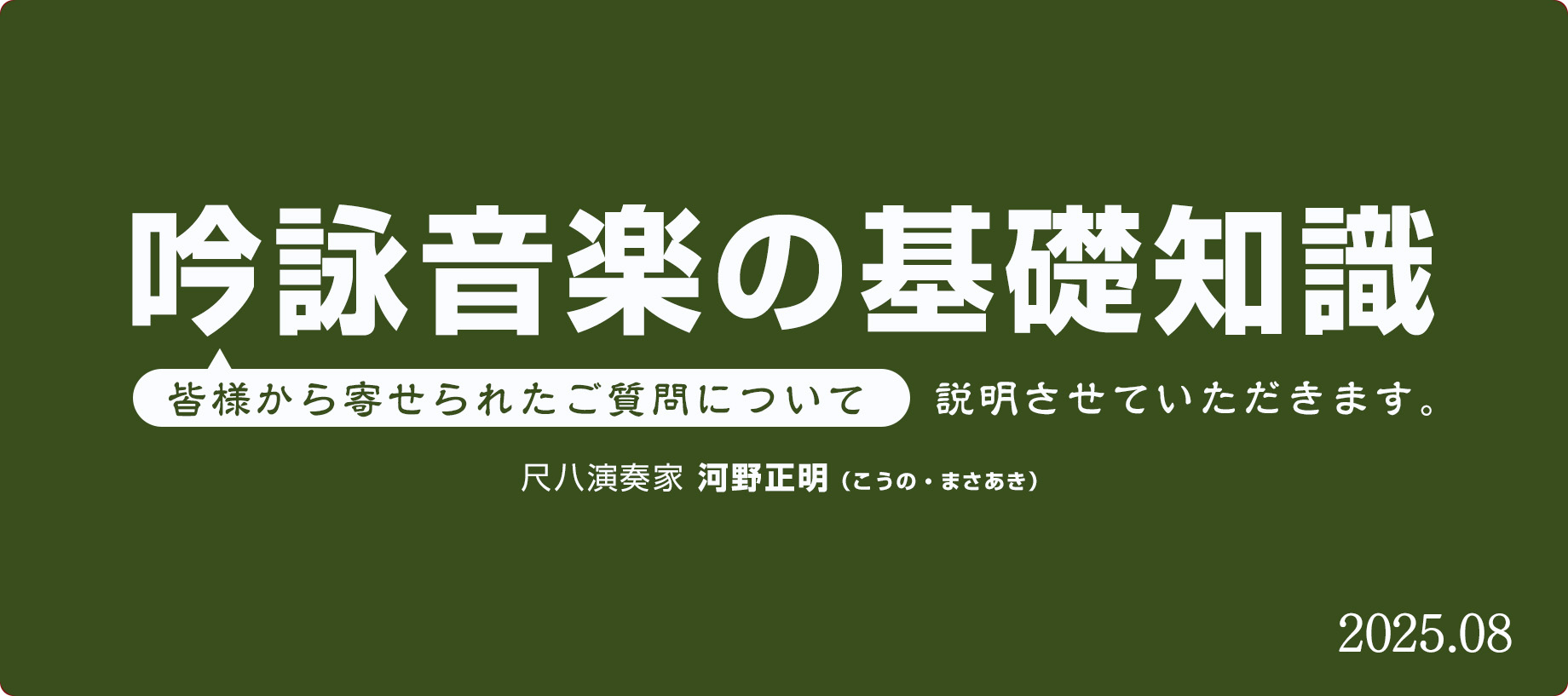
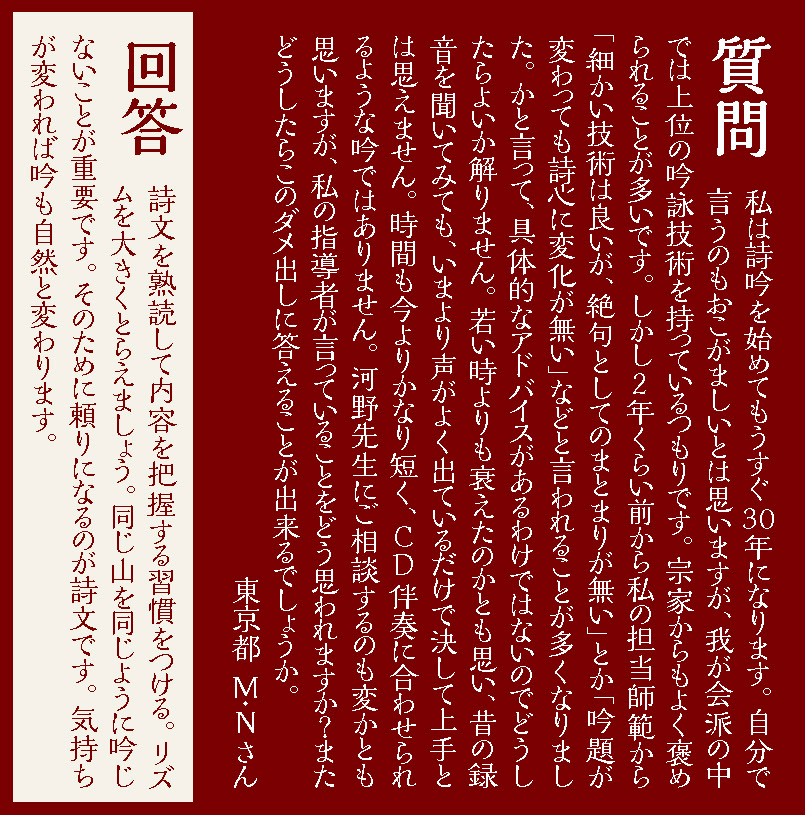
〈説明〉
貴方の指導者の方が、あなたの吟に対して的確なアドバイスを述べているかどうかは、あなたの吟を拝聴しなければなんとも申し上げられませんが、その内容は現在の吟詠家全般に対しても言える、極めて普通のことだと思います。
最近になって「まとまりが無い」とか「詩心が……」と言い始めたのは、あなたが上達して、不備な点が少なくなってきたため、指導に困ってのことではないでしょうか?
この二つの課題はあたりまえに必要なことですが、現在の吟界ではほとんどの方が顧みない項目となってしまっています。
吟詠は、文学であり、音楽であり、歴史、道徳、書道、漢詩の作詞など、幅広く教養を培うことのできる珍しい芸術だとおもいます。しかし現実は一世紀前と同じ「一声・二節」だけが注目され、その他の項目を指導している会派は極極一部です。
漢詩の見地から七言絶句の構成を見てみると各行が「二言・二言・三言」となっているので書き下しの訳文もこの区切りに沿って行われている場合が多いということはよく知られていることで、吟じ方もそれに倣って吟じます。また四行が二行ずつ一組になり、それぞれを聯と呼び一つの事柄を表しています。吟の節もこの二行を跨ぎ、二行で主音に戻り節が落ち着きます。そしてこの二つの聯が組み合わされて一つの絶句となっています。
詩文を何度も読むことにより、おのずと意味の区切れ目がはっきりするはずなのでわざわざ詩の構成を確かめることもないでしょうが、根拠として承知しておくとよいでしょう。
「絶句としてのまとまりが無い」と言われるのは、意味の連続している個所で息継ぎ、又は休止しているからではないでしょうか?つまり一つの詩になっていないと感じているのでしょう?絶句を吟じる時に途中で完全に休止符を置けるのは転句の前だけです。各行ごとに区切れるのでは? とお思いでしょうが吟詠のメロディーが連続しているので、音楽的には区切れません。詩文とは食い違いがありますが、昔の書生が詩文を覚えるために起句を吟じ出せば承句の頭が自然と口をついて出てくるようにメロディーを繋げたという説があります。転句と結句の関係も同じです。不合理に思える節付けですが、聯という観点からは合致していますので、今日までこのメロディーが用いられてきたのでしょう。
「トンボの、メガネは、水色メガネ、青い、お空を、飛んだから」この歌を唄うとき、文節ごとに息継ぎをする人はいません。楽譜上も息継ぎは「青い」の前だけです。ところが、これを詩吟のメロディーでうたうと
トンボの~オ~オ めがねは~ア~アア みずいろ~オオオ~オオ~オオ めがね~エエエ~エエ あおい~イイ~イ おそらを~ヲヲ~ とんだ~アアア~ア から~
元来、詩吟のメロディーとしての息継ぎは「みずいろ」の前と「お空を」の前だけでした。しかもこの童謡の場合、区切れ目は「青い」の前だけです。しかし詩吟の節で歌うと長さが長くなるのと、メロディーの違いから息継ぎが変わってきます。人によっては全ての節毎に息継ぎをする人もいます。元の詩文を考えてみますと、節毎に息継ぎなどする気にはならないと思いますが、習慣的に息継ぎをしてしまい、元の詩文が伝わらなくなってしまうのです。
せめて「トンボのメガネは」「水色メガネ」のまとまりくらいは維持したいものです。このまとまりを成り立たせるのは詩文への意識です。詩文優先で吟じれば、たとえ途中で息継ぎをしてもそれぞれの文節は繋がります。これを「意連」と言い、音楽や書道などで気持ちが一貫している意味を表します。詩文を優先すれば、なんど息継ぎをしても「トンボのメガネは水色メガネ」と繋がって聞こえるのです。たとえ、間に節が有ろうとも意味がつながって聞こえるものです。息継ぎと休みは違います。「意連」の間は息継ぎをしても間は空きません。
音楽の分野では、リズムを小刻みに取るのは初心者と言われます。2小節ごとのリズムとして演奏する場合と、4小節まとめた演奏では曲の流れが変わってきます。リズムは大きくとった方が節の変化が豊かになり、いわゆる「大人の演奏」になるといわれます。
詩文優先の気持が有れば自然と大きな塊ごとに吟じるようになりますし、そのことがそのまま詩心表現に繋がります。「詩文が伝わる」という最低限の条件が満たされるわけです。
このような吟じ方ができるようになると、言葉の後の節(山)の吟じ方も変わってきます。意連の間は常に詩文が頭にあるわけですから、悲しい詩文の節に楽しく明るい発声はできるはずが有りません。同じ節でも詩文が変われば吟じ方も変わるというのは常に詩文が頭にあるということです。一にも二にも詩文が頼りです。昔からこの状況を強いられているのが剣詩舞の皆さんです。詩文によって振りが変わるのですから常に詩文の内容が伴ってしまう。片や、詩文の内容に拘らずとも声にして発すれば一応責任を果たせる吟詠の立場は、とかく詩文から心が離れ、声と節回しだけになってしまいがちです。気を付けましょう。
※こちらの質問は『吟と舞』2021年7月号に寄せられたものです