 トップページ
トップページ ×
×
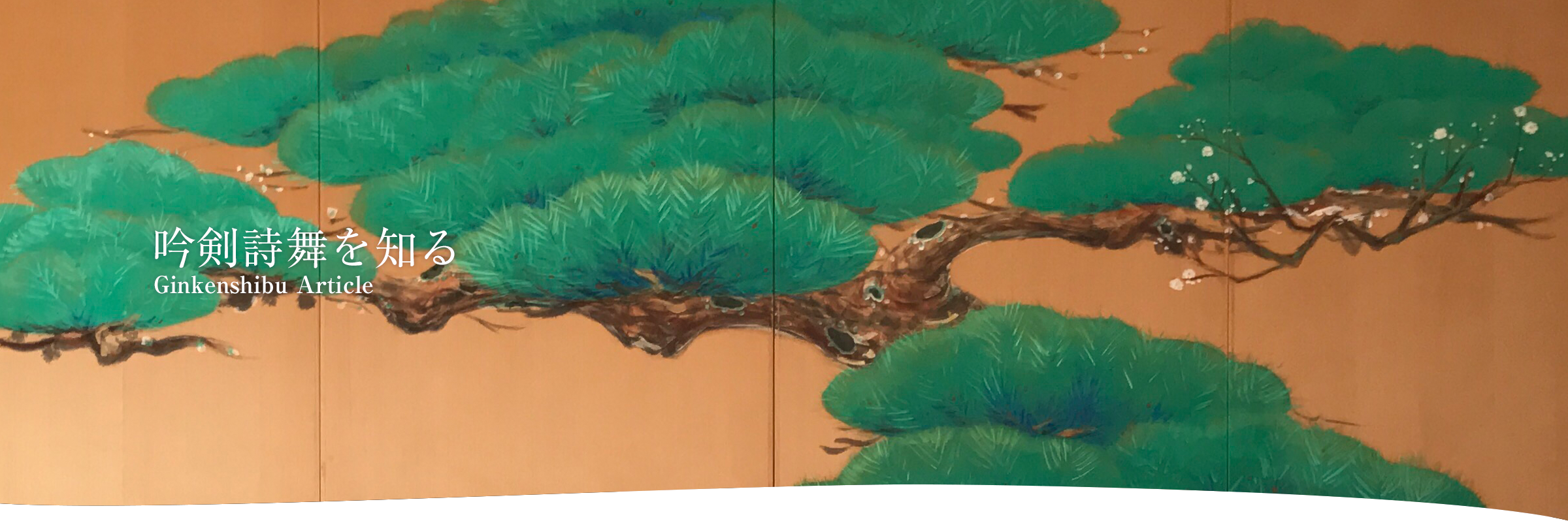
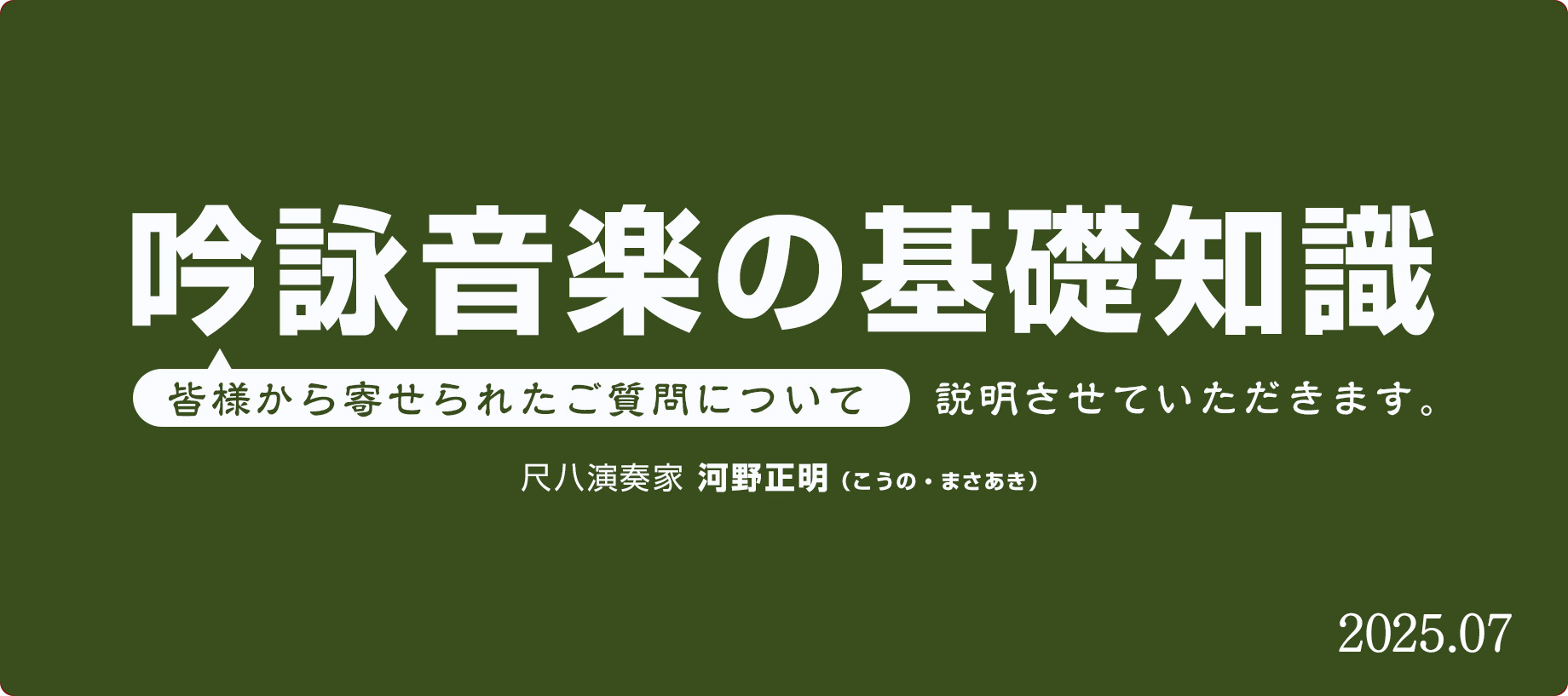
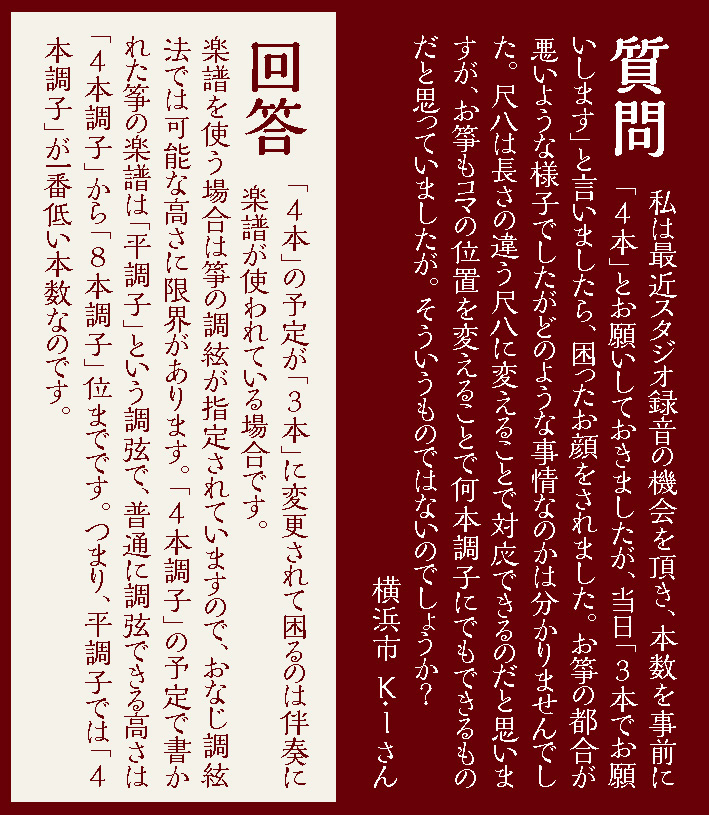
〈説明〉
一般的に一吟会のようなときに箏の伴奏をするときは大抵アドリブで演奏することが多いと思います。アドリブの場合は本数によって調絃の種類を変えて、「4〜8本」の場合は「平調子」、「水2本~3本」の場合は「中空調子」、「水4本〜1本」の場合は「雲井調子」という調絃をします。
ピアノのように半音刻みで7オクターブ以上(88鍵)もある場合は何本調子でも演奏できますが、箏は13の絃しかありませんので、詩吟に必要な音のみを設定しても2オクターブ半位です。因みに箏の絃の名前は低い方から、一二三四五六七八九十斗為巾です。平の時は五~十までを「ミファラシドミ」と調弦し、中空の場合は三~八までを「ミファラシドミ」、雲井の場合は二~七までを「ミファラシドミ」と調絃するのです。
伴奏をするうえでは主音(ミ)の低音が欲しいので「一」の絃が「ミ」となる平調子が都合よいのですが、音域の都合で他の調絃にすることも少なくありません。
例えば「4本調子」の予定で「平調子」に調弦した場合、平調子のままこれ以上低く調弦しようとしますと「一」のコマ(筝柱コトジ)をさらに左へ移動しなくてはならず、龍尾に阻まれ更に1本下げることはほとんど無理です。どうしても必要な場合は背の低い筝柱を使ったり一の絃を緩めたりすることもありますが、どちらも絃の張りが緩くなり、音が弱くなりますし、背の低い筝柱(小柱コジ)は演奏中に外れる危険があり、またいったん絃を緩めてしまうと元に戻すことが難しく、締め直すためには職人技が必要となります。その為、「一」や「二」の絃を緩める必要が生じた場合は順番をその日の最後にして頂くことが有ります。
また、その場で楽譜を書き直す方法もありますが、箏の場合、「手法」というものがあり、機械的に平行移動した楽譜は使えません。その為、2分間の吟の伴奏を書き直すのに1時間以上かかりますので現場では無理があります。
弦楽器のほとんどがその絃の締め具合をネジによって調節する構造になっていますが、箏だけはネジの構造が有りません。「引っ張って結ぶ」という驚くべき構造です。13絃の筝以外の筝はネジが使われますが13絃の場合はほとんどネジの構造はありません。理由は、ねじ止めにすると音色が悪くなる為とのこと。十七絃や二十絃などはネジを用いています。同じ邦楽器の仲間でも三味線(三絃)や琵琶は糸巻きがあります。箏も琵琶も渡来の物ですが、当初より現在とほとんど同じ構造です。ギター、バイオリン属、ハープ、シタール、バンジョー、ピアノ、揚琴など弦楽器と言われるものはみな絃をネジ止めする構造です。筝以外にネジ止めの無い弦楽器を無理やり挙げれば、古代の呪術の為の鳴弦の弓くらいです。
大陸の筝は、ネジ止めに変化しただけでなく、ハープのように、足でペダルを踏むことによって、転調できるような改良もされています。また琵琶も大陸では大きく変化し、渡来当初の形のまま演奏されているのは日本だけです。
日本では筝のみならず、楽器を機能的に改良することを好まなかったようです。ただ、音質の為に材質に拘ったり、音響の為に内部に細密な彫刻をほどこすなど、興味の向かう先が内向的と見るべきでしょうか。
話が筝から逸れてしまいますが、日本の弓と西洋の弓(アーチェリー・ボーガンなど)を比べてみても、明らかにその目的が違うことに気付きます。日本の弓は相当の熟練者でないと的に矢は当たりませんが洋弓は誰が使ってもある程度的に近いところに矢は飛びます。弓の稽古にしても、日本の場合は所作に拘ること8割で、的を外しても所作が良ければ褒められます。しかし、この所作を褒められるようになるまでが大変な修行であることを知る人はわずかです。弓は武器として発達するものと思いますが。日本の場合は精神鍛錬の道具として発達し、弓自体は機能と同時に美しさも求められました。その点は刀も同じです。戦いの道具、武器であると同時に信仰の対象でもありました。丈夫でよく切れるばかりでは名刀とは呼ばれません。優れた機能の上に、それに沿った美、機能美が求められたのです。名人が鍛えた刀はそれなりの武人が持つべきものとされるのは、和弓を熟練者のみが使えるのとよく似ています。
初心者の琵琶と尺八は公害。ギターなら調絃さえ正しければ、初心者といえども公害にはなりませんが、琵琶は正しく調絃することすら難しく、また、調絃が正しくても、弾き始めて数秒で音程が狂ってしまう為、まともな演奏ができるようになるのは至難の業。また、フルートは音さえ出れば初心者でも公害にはなりにくいのですが、尺八の場合は音が出ても音程が定まらないので公害になり易いのです。箏の場合も琵琶ほどひどくはないものの、一曲弾き終わった頃はかなり音程が乱れます。しかし「名人は最後まで音程の乱れを感じさせないものだ」と舩川利夫先生がおっしゃっていました。和楽器は魅力的で不便な楽器です。
※こちらの質問は『吟と舞』2021年6月号に寄せられたものです