 トップページ
トップページ ×
×
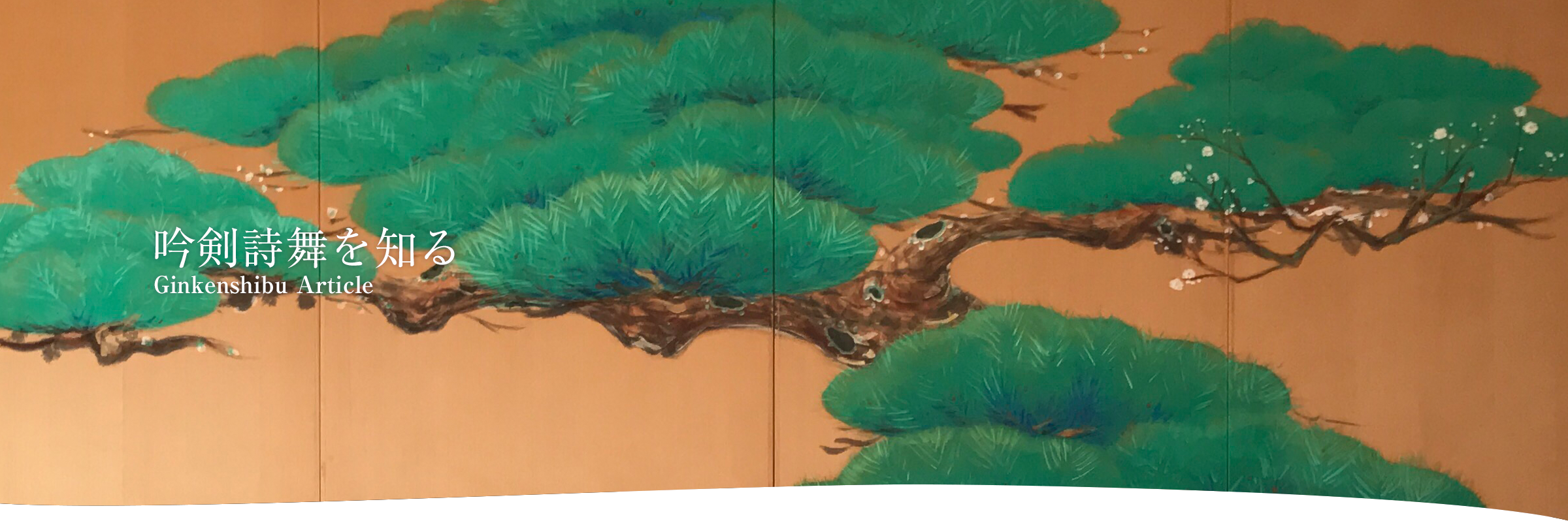
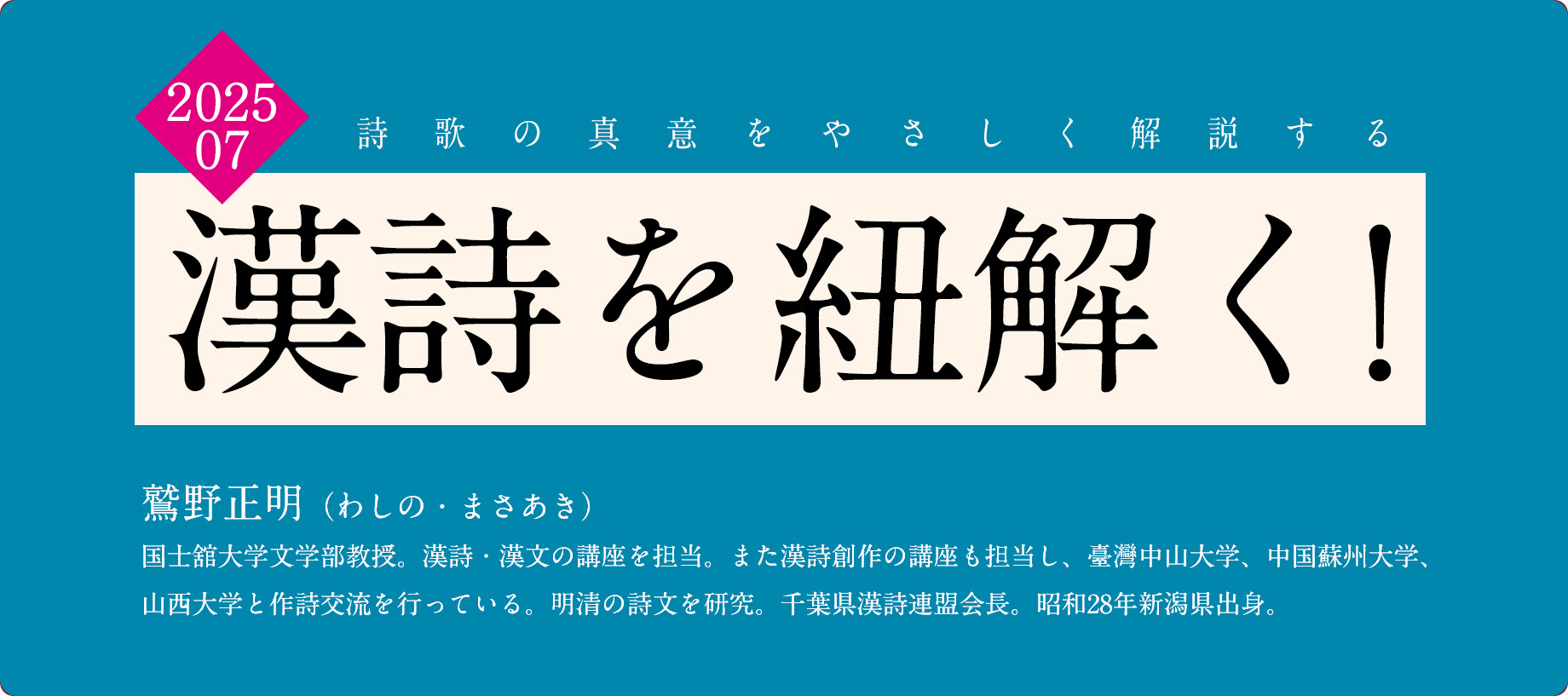
王維「雑詩」
梅は中国原産のバラ科の植物です。中国最古の詩集『詩経』(紀元前五世紀頃成立)に「摽ちて梅有り、其の実七つ。我を求むる庶士、其の吉に迨べ」(召南・摽有梅)とあります。梅が熟して落ちることを「摽」と言い、女子の婚期を暗示します。
これは梅の果実ですが、花を詠う初期のものには、前漢の劉向(前七七~前六)の『説苑』奉使篇に、越国の使者の諸発が「一枝の梅を執て梁王に遺る」とあります。南朝の宋代には、陸凱が范曄(三九八~四四五)に梅の花の一枝を折って駅使に託し、「聊か一枝の春を贈る」という詩を添えています。ここから「一枝の春」は梅を指すようになりました。
中国歴代の詩人は梅を愛し、さまざまなテーマで詠っています。梅を偏愛する詩人も多く、宋の林逋(九六七~一〇二八)が梅を妻とし鶴を子とした話は有名です。明の高啓(一三三六~一三七四)も梅好きとして知られています。
唐の王維(六九九?~七五九)は「雑詩」で寒梅を詠っています。三首連作の其の二。
客自故鄕來[客故郷より来たる]
應知故鄕事[応に故郷の事を知るべし]
來日綺窓前[来るの日綺窓の前]
寒梅著花未[寒梅花を著けしや未だしや]
〈君はわたしの故郷からやって来たから、きっと故郷のことを知っているに違いない。故郷を出発する日、飾り窓の前の寒梅は花をつけていましたか。〉
「客」は旅人。自分の故郷からやってきました。そこで故郷のことを知っているに違いないと、出発の日「綺窓の前」の寒梅の花はもう咲いていましたか、と質問します。「綺窓」はあや絹を張った美しい飾り窓です。そこには女性がいます。その女性は、もちろん妻。妻のいる部屋の前の寒梅は咲いていましたか、とは、つまり妻は息災ですかということ。直接妻の安否を尋ねるのではなく、部屋の前の花が咲いたかどうかを尋ねるのです。奥ゆかしいですね。「故郷」と「来」を二回ずつ使っているのも、妻への思いの強さが伝わってきます。
「雑詩」三首は、それぞれ関連しながら詩の主人公と内容が変わります。其の一は、庶民の女性が旅に出ている夫を思う。其の二は、旅に出ている士大夫(エリート階級)の男性が妻を思う。其の三は、寒梅が開いたのに男性が来ない、と宮女が悲しむ内容になっています。
其の一と其の三も見ておきましょう。其の一。
家住孟津河[家は住す 孟津河]
門對孟津口[門は対す孟津口]
常有江南船[常に江南の船有り]
寄書家中否[書を家中に寄するや否や]
〈家は孟津河にあり、門は孟津口に向かいあっている。いつも江南から船が来るけれど、私に寄せた手紙はあるかしら。〉
商売かなにかで出かけている夫からの手紙を妻が心待ちにしています。其の三。
已見寒梅發[已に寒梅の発くを見]
復聞啼鳥聲[復啼鳥の声を聞く]
愁心視春草[愁心春草を視]
畏向玉階生[玉階に向かって生ずるを畏る]
〈もうとっくに寒梅の開くのを見、また鳥の鳴き声も聞きました。(それなのにあの人はどうして来ないのかしら。)さびしい思いで庭の草を見つめていると、階段まで草に埋もれてしまいそうで心配だわ。〉
「愁心」は愁える心、さびしい気持ちを表します。「春草」は、旅に出たまま帰ってこないうちに、萌え出した春の草を言います。別離を暗示することばで、詩によく使われます。「玉階」は大理石の階段。詩の主人公は男性の来訪を待つ宮女です。
「雑詩」三首は男女それぞれの、相手への思いを民謡調で詠っています。其の二は「旅に出ている夫が妻を思う詩」ですが、王維が自分のことを詠ったのだ、と、一般的に解釈されています。王維は三十二歳で妻を亡くしますが、後妻はもらいませんでした。
梅は春のまだ浅い時期に、他の花に先んじて咲きます。そこで「寒梅」と言い、また「花魁」と言います。「魁」はさきがけです。「雑詩」では其の二と三に寒梅が詠われます。王維が故郷の家にいたときいつも見ていた花だったのでしょう。恋する人へのやさしい思いと、故郷へのやわらかな思いが「寒梅」にこめられています。
