 トップページ
トップページ ×
×
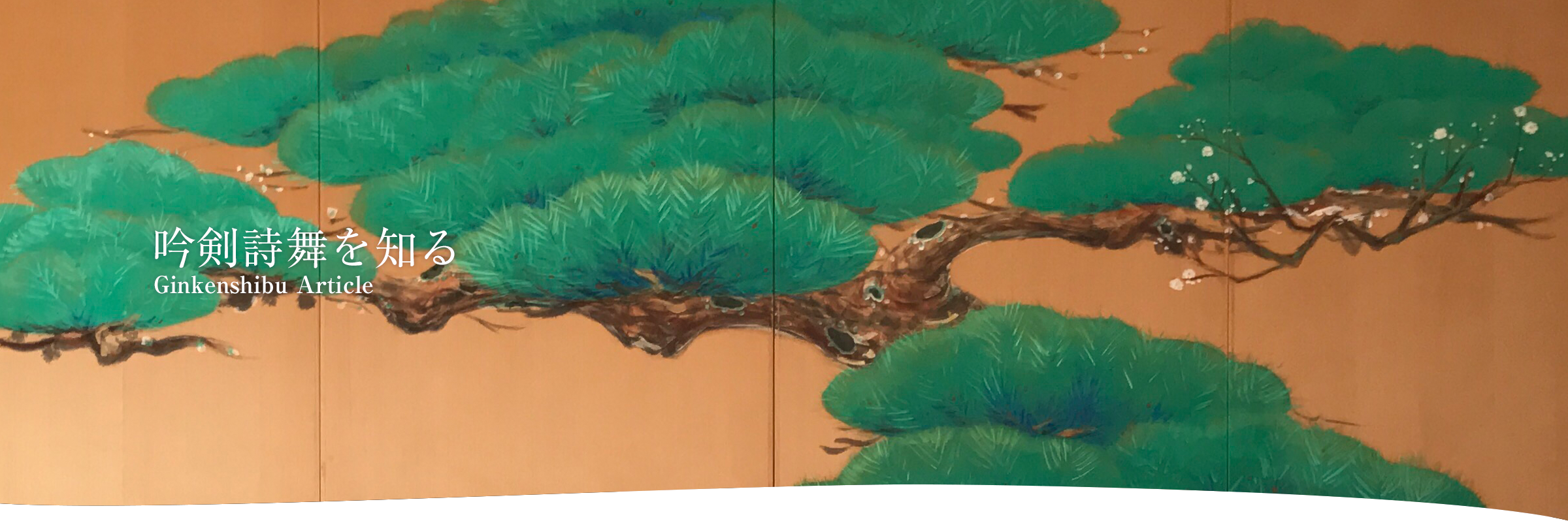
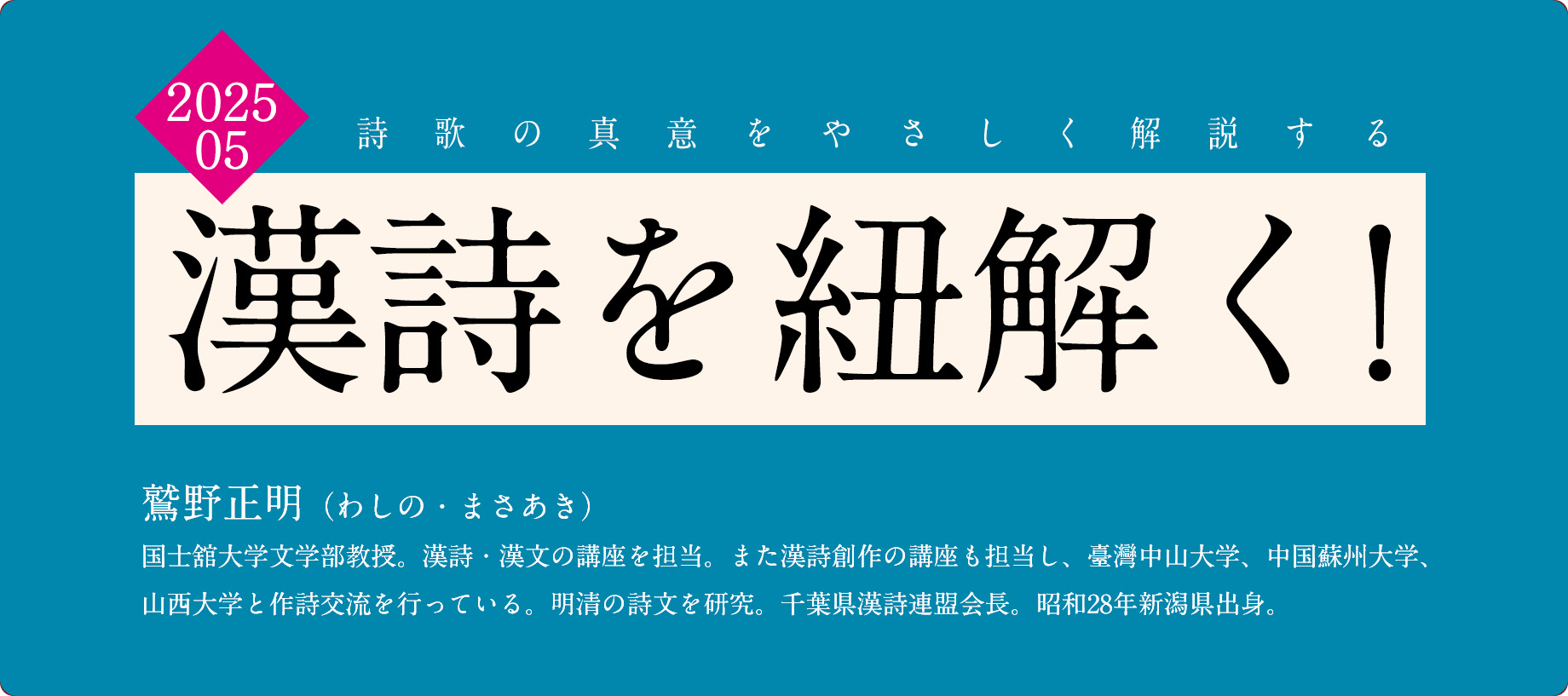
白居易「菊花」
晩秋のころ菊の花が咲きます。他の花があらかた散っているため、寒さのなかで独り咲く菊の花は清々しく、その美しさがいっそう際立ちます。白居易の「菊花」は、まさにその様子を詠います。
一夜新霜著瓦輕[一夜新霜瓦に著いて軽し]
芭蕉新折敗荷傾[芭蕉は新たに折れて敗荷は傾く]
耐寒唯有東籬菊[寒に耐うるは唯東籬の菊のみ有って]
金粟花開曉更淸[金粟の花は開いて暁更に清し]
〈夜が明けると、初霜が降りて瓦がうっすら白くなっている。芭蕉は新たに折れて、やぶれたハスの葉も傾いている。そうした中で寒気に耐えているのは、ただ東の籬の菊だけ。金のような美しい花が咲いて、暁の風景がいっそう清らかになっている。〉
初霜が降り、芭蕉が折れ、敗荷が傾き、と植物の衰えたなか、寒さに耐えて独り超然と咲く菊の花を「金粟」と表現して、その清らかさと美しさを強調します。第三句の「東籬の菊」は陶淵明(陶潜)の「飲酒」其の五を踏まえています。
采菊東籬下[菊を采る東籬の下]
悠然見南山[悠然として南山を見る]
菊の花は、俗世を離れて悠然と生きる陶淵明と重ねられ、陶淵明の代名詞となり、隠者の象徴となりました。陶淵明ははじめ官僚となりましたが、宮仕えが厭になり「帰りなんいざ」と「帰去来の辞」を作って園田に引きこもります。ふる里の庭にはもともと三本の小径があり、菊や松が植えてあったようです。「松」も三本の小径「三径」も、隠者の象徴です。ふる里の三本の小径は荒れてはいるものの、まだその松と菊があった、「三径荒に就いて、松菊猶お存す」と、陶淵明は「帰去来の辞」で言っています。
隠者と言うと山林に住んでいる印象がありますが、陶淵明は町の中に住んでいました。それでも隠者として生活ができるのは、心の持ちようだと言います。
結廬在人境[廬を結んで人境に在り]
而無車馬喧[而も車馬の喧しき無し]
問君何能爾[君に問う何ぞ能く爾るやと]
心遠地自偏[心遠ければ地自ら偏なり](「飲酒」其五)
隠者はお金も地位もありませんが、自由があります。その隠者も、山林に住む隠者は「小隠」、町の中に住む隠者は「大隠」と言って区別する言い方が晋の時代に生まれました。陶淵明は「大隠」ということになります。
一方、白居易は高官となって自由もありましたので、自らを「中隠」と言っています。
大隱住朝市[大隠は朝市に住み]
小隱入丘樊[小隠は丘樊に入る]
丘樊太冷落[丘樊は太だ冷落]
朝市太囂諠[朝市は太だ囂諠]
不如作中隱[如かず中隠と作りて]
隱在留司官[隠れて留司の官に在るに](「中隠」)
「留司」は、分司東都という名ばかりの官です。白居易は陶淵明を慕い、「陶潜の体に效う詩」「陶公の旧宅を訪う」などの詩があります。
この詩では折れた芭蕉と葉の破れた荷が詠われています。芭蕉は庭木としてよく植えられていました。中唐の竇鞏は「隠者を訪ねて遇わず」で、訪ねてきたことを知らせるために芭蕉の葉に名前を書いておきたいが、芭蕉は秋には耐えられないので書いても無駄かな、と詠っています。
欲題名字知相訪[名字を題して相訪ぬるを知らしめんと欲するも]
又恐芭蕉不耐秋[又恐る芭蕉の秋に耐えざるを]
ハスは荷のほかに、蓮、芙蓉、芙渠、菡萏、藕などとも表記され、古代から親しまれていました。晩秋になって枯れたハスや敗れた葉は敗荷と呼ばれました。晩唐の李商隠は、破れた恋と破れたハスを重ねて次のように詠っています(「夜冷」)。
西亭翠被餘香薄[西亭の翠被余香薄く]
一夜將愁向敗荷[一夜愁いを将って敗荷に向かう]
宋の蘇軾は葉が無くなったことを次のように言います。
荷盡已無擎雨蓋[荷尽きて已に雨に擎ぐるの蓋無し]
「金粟」は、この詩では菊の花のことですが、金銭と穀物を表したり、「桂」、金木犀を言うこともあります。
夏目漱石『草枕』の初めの方に、陶淵明の「菊を采る東籬の下、悠然として南山を見る」と王維の「竹里館」の全詩が引用されています。
