 トップページ
トップページ ×
×
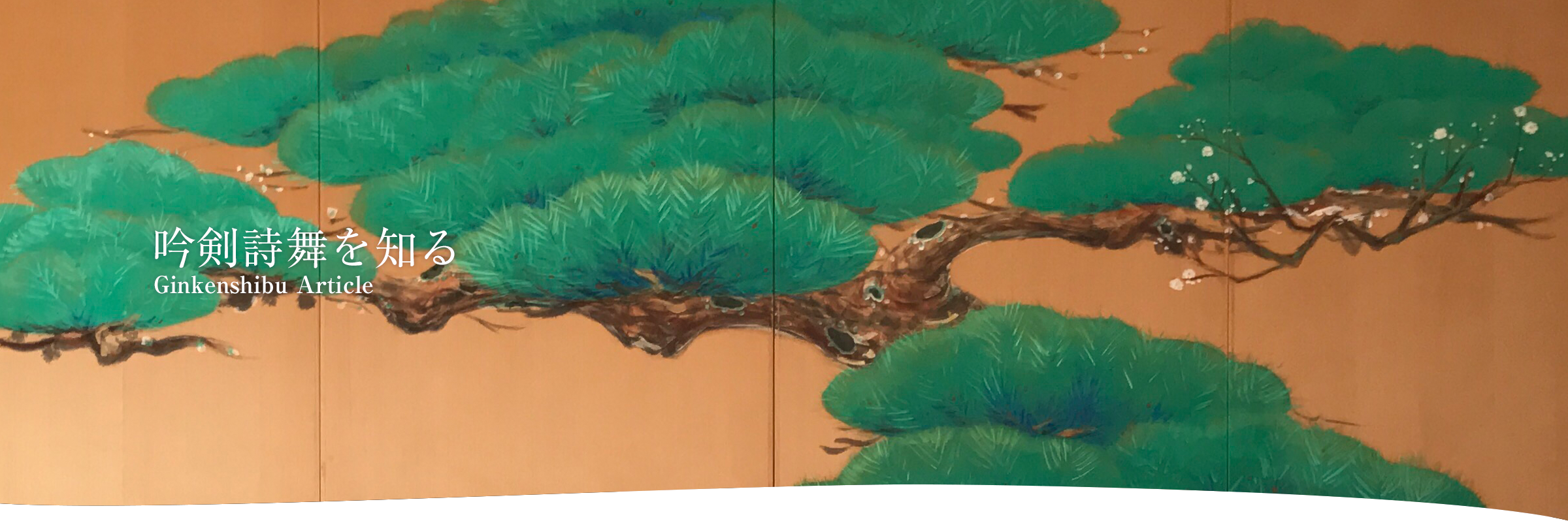
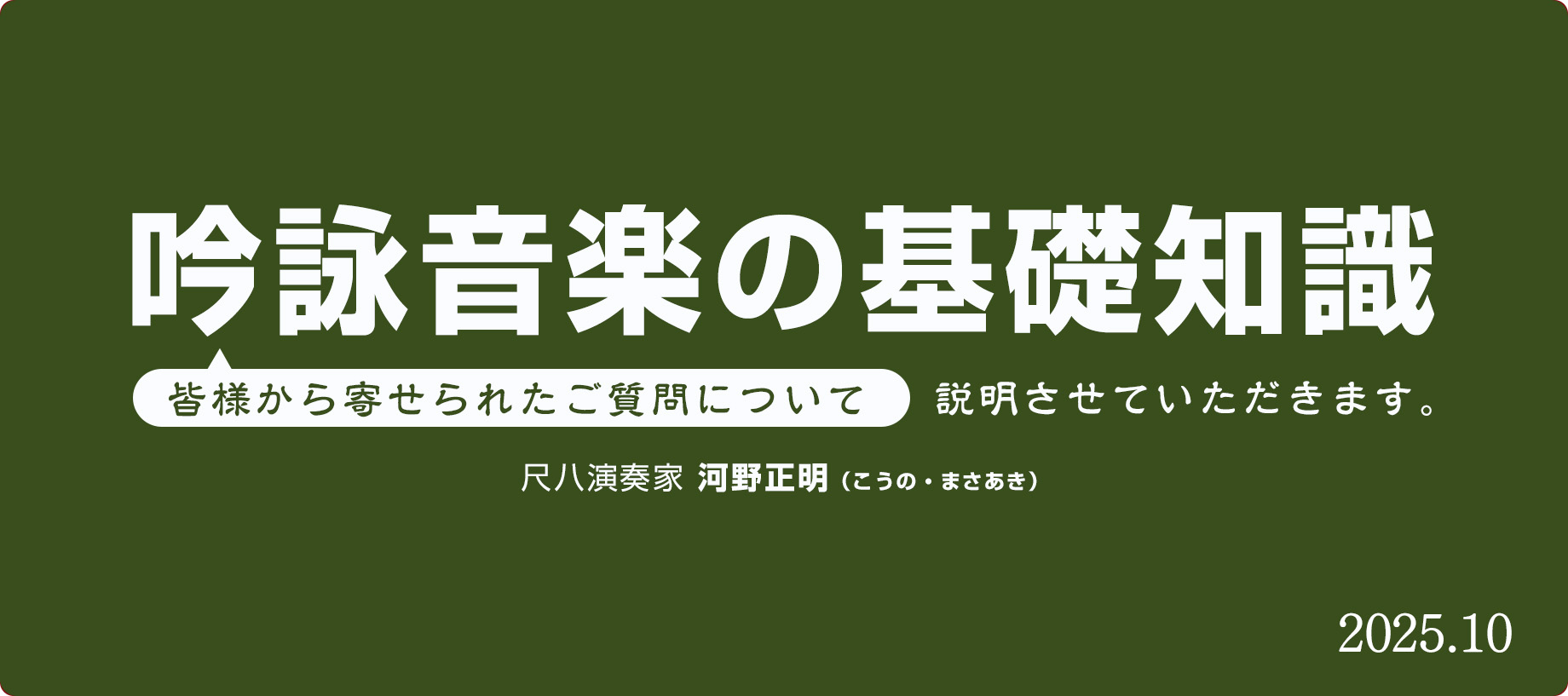
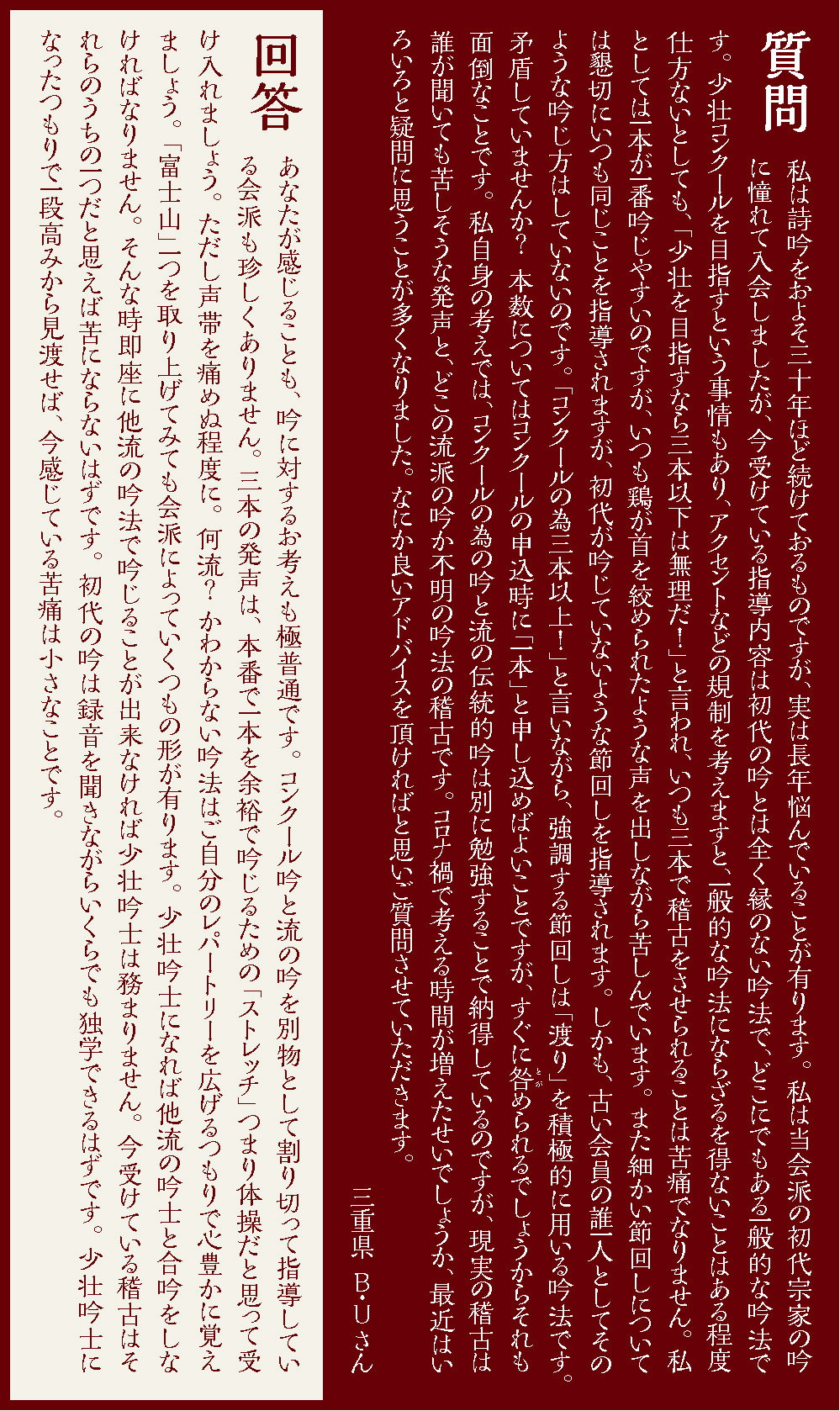
〈説明〉
本数の問題については、この講座や講習会などで何度となくお話ししてきましたように、どんなコンクールでも本数が高いほど有利という法則はありません。何度もご紹介しました例ですが、一つの部門で本数の一番低い人が優勝した例もあります。
財団のコンクール史の中で、ある時からプログラムに登録本数を載せないことになりました。それは、本数が審査に影響を与えないようにとの配慮と、吟界全体に対して「本数と成績は無関係」であることを知らしめるための変更でした。
しかし、現実はなかなか好転せず、高い本数にこだわり、聞く人を苦しめる吟者のなんと多いことでしょう。本数に余裕が無ければ吟そのものに余裕が無く、苦しそうに聞こえるのは当たり前のことです。昔、主に東の地域で、悲憤慷慨を表現する詩吟がもてはやされた時期、転句に高音のミを用い、しかもウラ声を使わずオモテ声で無理やり怒鳴る吟法がありました。高音の「ド」と「ミ」では4本もの音程差がありますのに、ウラ声を使わないのはまさに悲憤慷慨の表現の為であり、この影響を受け継いだ流派には、「転句は怒鳴るべし!」とし、「転句のガナリ」がコンクールの好成績につながるということもありました。この場合は苦しそうに聞こえるのが良いことであり、目的であったのですから、多少音程が届かずとも問題ないわけです。しかし、今日では流行っていません。
音程は届かないと目立ちます。しかし、設定の本数が高すぎて高音の節が上がりきれないことの聞き苦しさより、「最近本数が下がったね」と思われることの方が苦痛・屈辱と思う吟者がとても多いのです。これはとんでもない勘違いです。高い節が上がりきれないことの方が百倍恥ずかしいと思ってください。
流統の吟法とは違う吟を指導されているとのことですが、おそらくその指導者としては気に入っている吟法なのでしょう。なんとか貴方に覚えてもらい、広めたい気持ちが有るのではないでしょうか?
話は少し変わりますが、室町時代の終わりころ、浄瑠璃という、三味線を伴奏に物語を唄い語る芸術が起こり、江戸時代に全盛を極め、落語にも「寝床」という演目で「大家の浄瑠璃」に付き合わされる長屋の住人と大家のやり取りが語られますが、それほど浄瑠璃は猫も杓子も夢中になった芸能のようです。この全盛期に沢山の流派が出来、義太夫節・常磐津節・清元節・半太夫節・河東節・外記節・大薩摩節・一中節……など、多くの名人と言われる人が登場したようです。私などは浄瑠璃には疎いので、学生の頃はそれぞれ別の芸能かと思っていました。例えば長唄と謡曲のように。しかし舩川利夫先生に師事してから、全部浄瑠璃の流派名であることを聞かされ唖然としました。近年では常磐津・清元・義太夫などのように、「節」を省略することが多いので、長唄・地歌・謡曲などに並ぶ存在と思ってしまったのです。このように流派が増えたことに少し関係があるかもと思われる浄瑠璃家の言葉を紹介します。
一中節の二世 都一廣(人間国宝)は「自分自身の特徴を、知らぬまに稽古で教えている人が多い。師匠という立場の者は、お弟子が気付かぬ本人の長所・特徴を引き出してあげることが肝腎で、やたらと自分の芸風を押し付けるのは間違っている」と言い切っています。「自分のコピーを作るな、必ず悪いところばかりが目立つようになる」とも言っています。私も、恩師 舩川利夫先生から同じことを言われましたが、時すでに遅し、さんざん舩川節を身に着け、自慢していた頃でした(笑笑)
※こちらの質問は『吟と舞』2021年9月号に寄せられたものです