 トップページ
トップページ ×
×
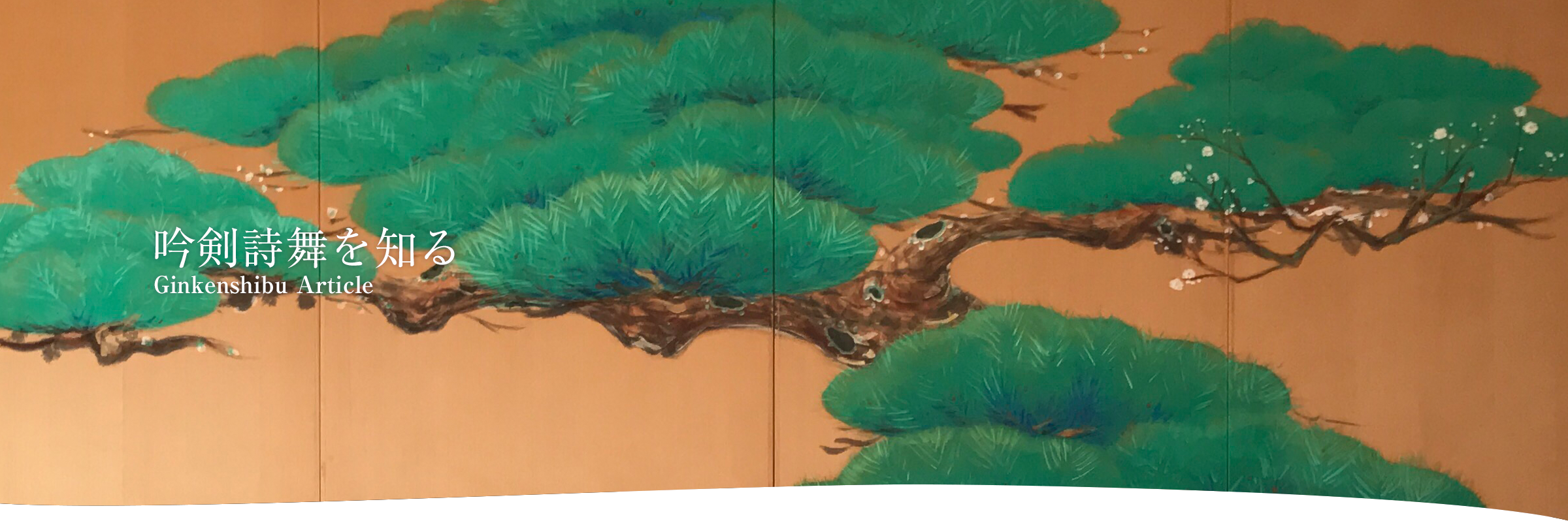
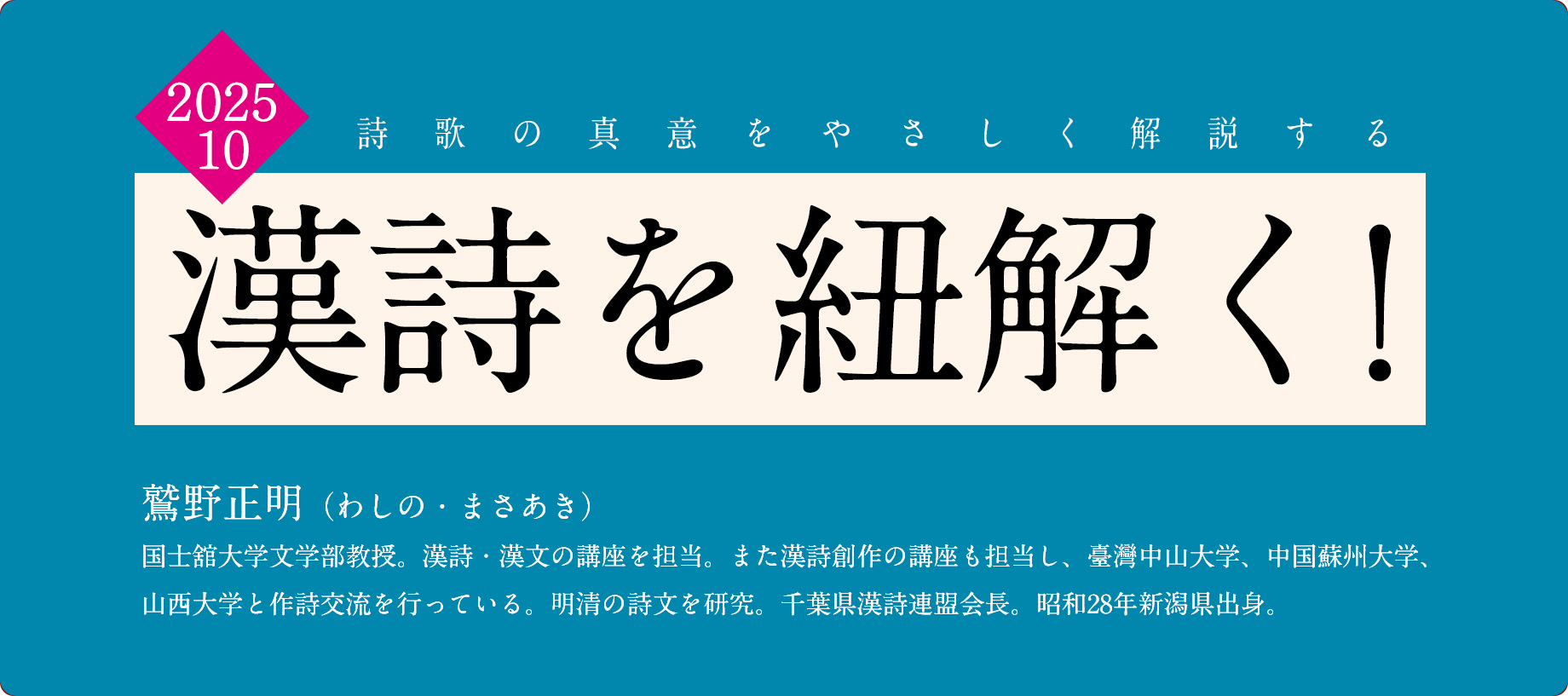
佐野竹之助「出郷作」
前回の最後に「詩語の選択と連絡、全体の構成、とても参考になります」と書きました。そこで今回は、その言葉の選択・連絡・全体の構成について少し説明したいと思います。
漢詩を読むとき私たちはまず訓読をします。そして言葉の意味を理解し、句の意味を理解し、全体の意味を理解し、作者の「思い」を感じ取ります。「思い」はその詩の主題(テーマ)とともに詠われます。作者は、「思い」を伝えるために、主題に沿う言葉を選び、主題を明らかにするために無駄な言葉を省き、すべての言葉が連絡し合い、絶句の場合は四句を起承転結で構成します。こうして詩からおのずから作者の「思い」が立ち現れてきます。言葉が主題に沿わなかったり、言葉が繋がっていなかったり、構成がいいかげんだったりすると、主題も「思い」も読者に伝わりません。「出郷の作」はどうでしょうか。
決然去國向天涯[決然国を去って天涯に向う]
生別又兼死別時[生別又兼ぬ死別の時]
弟妹不知阿兄志[弟妹は知らず阿兄の志]
慇懃牽袖問歸期[慇懃袖を牽いて帰期を問う]
題名が「出郷」ですから主題は「別れ」になります。しかも承句の「死別」から、死を覚悟した別れであることも分かります。承句は「生別」「死別」と「別」を二度言って別れを強調し、かつ主題の別れを、生別がすなわち死別であると言います。「決」ケツ「国」コク「別」ベツのように音読みすると詰まる音(入声と言います)の漢字を使って、強い意志を音からも感じられます。言葉がスムーズに繋がって意味は明瞭です。しかしこれで終わったら、決意の表明または別れの説明になってしまいます。
詩の第三句は転句で、前半の視線を転じて別れの一場面を詠います。父母に別れを告げるという詠いかたもできます。が、ここでは幼い弟妹との別れに焦点を当てます。弟妹は兄の「志」を知る由もなく、無邪気に、いつものように、袖を引いていつ帰ってくるのと尋ねます。「志」は前半の二句で言う「死の覚悟」です。弟妹の描写は、兄の袖を引くといういつもの何気ない動作と無邪気な問いかけだけです。兄の「志」を理解できない幼い弟妹の普段のふるまいによって、情に絆され、別れの悲しみが湧いてきます。
詩の主題は一つだけです。「思い」は誰もが生まれながらに持っている「情」に訴えます。この詩では幼い弟妹の無邪気さが前半の固さと絶妙なバランスをとりながら、「情」を誘います。言葉に無駄がなく、すべの言葉が活きてつながり、起承転結の構成もきちんとしています。それ故一読して主題も作者の「思い」も伝わってきます。
私たちはいつも名作を読んでいますから、言葉の選択、連絡、全体の構成という三要素をそれほど意識しませんが、詩を読む際には(詩を作る際にも)是非この三要素に気をつけてください。
絶句は四句という短い詩ですから、細かな背景は描かれません。読み味わう際には作者の経歴や作詩の時期が分かれば、鑑賞がより深まります。作者の佐野竹之助は水戸藩士で、安政七年(一八六〇)三月三日、桜田門外で大老の井伊直弼を暗殺した一人です。首級を挙げたのち、刀傷を負いながらも決起の趣意書を提出して亡くなりました。二十二歳でした。「生別」が「死別」となった悲しい別れです。
