 トップページ
トップページ ×
×
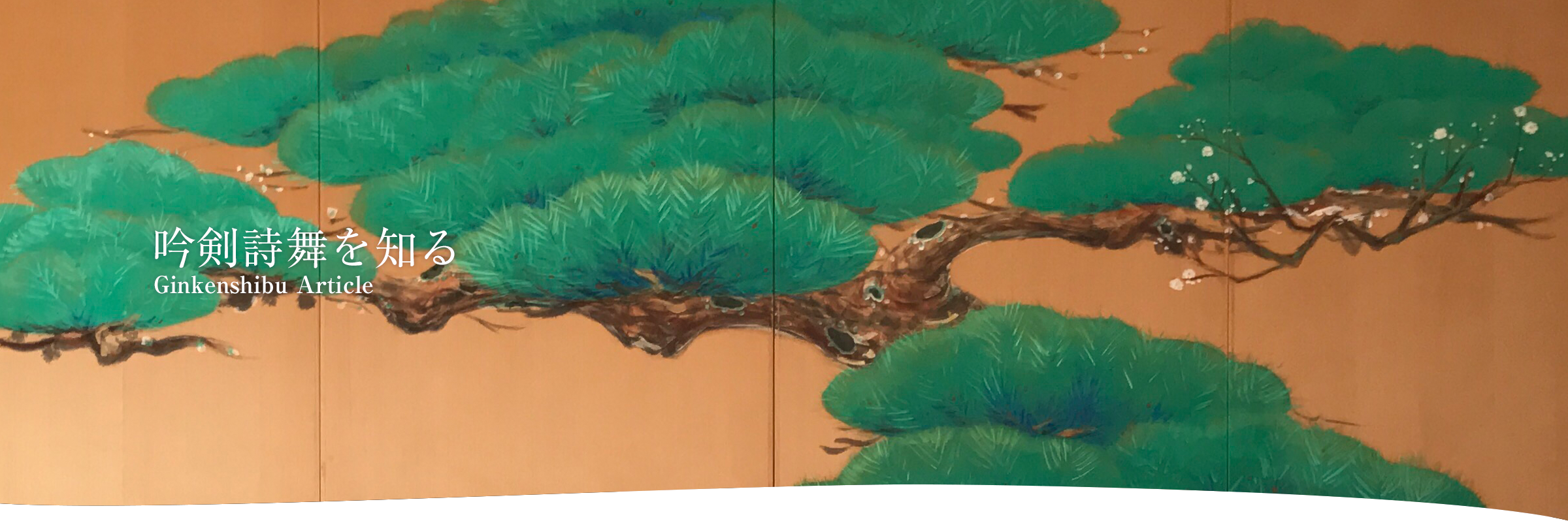

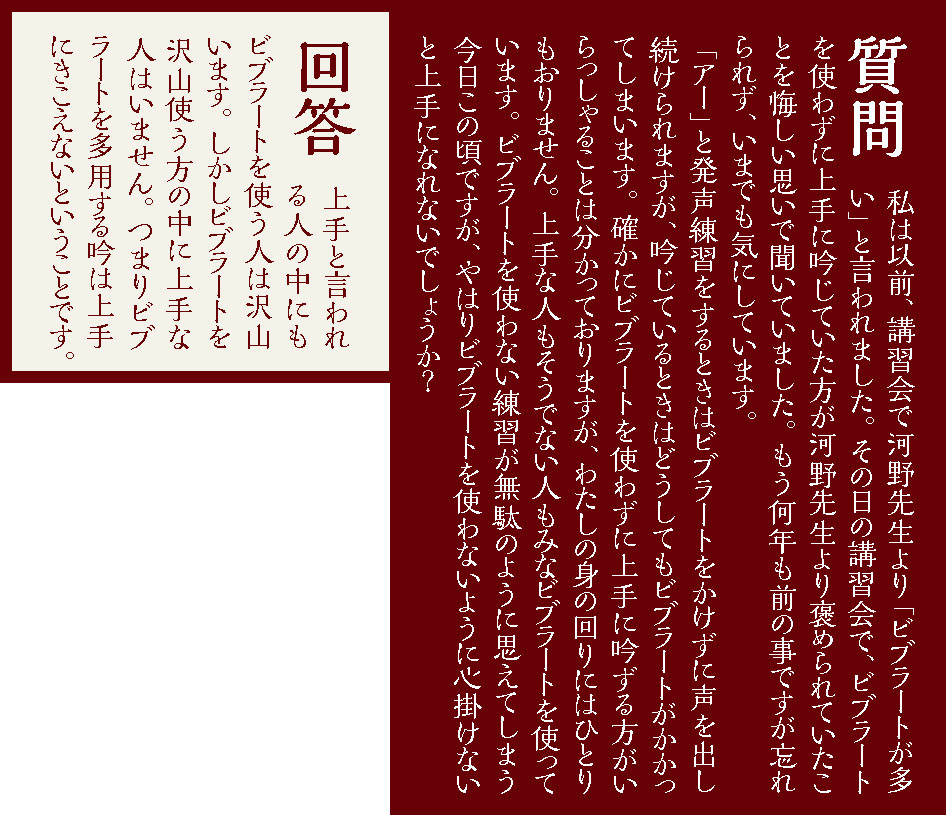
〈説明〉
吟詠にビブラートを使ってはならないという決まりはありません。しかし日本古来の様々な歌には伝統的にビブラートは使われてきませんでした。これがなぜかという問いには明解な答えを用意しておりませんが、伝統的にそうであったためにビブラートが多いと違和感があるのでしょう。去年、ある葬儀に出席しましたらお経にビブラートを使うお坊さんがいました。お経と言う雰囲気ではありませんでした。現在、吟詠にビブラートを使う方が多くなりましたが、最近はあまり口うるさくとがめる方は少なくなりました。ビブラートを使う人の方が多くなったことは確かです。この傾向が更に極端になると、もはや「ビブラートは控えましょう」と提唱することの方が奇異な存在になってしまうかもしれません。しかしビブラートの無い吟を聞いた後にビブラートの多い吟を聞けば明らかに騒がしいことが分かります。ただ、聞き比べる機会が少なくなってしまったことも事実です。
最近テレビ番組でバイオリンコンチェルトを聞きましたが、その時のソリストが極端にビブラートを多用する人で、耳障りで聞いていられませんでした。若い日本人の女性で最近よく活躍されている奏者と言う紹介でした。私自身の感覚がおかしくなったのかと思いましたが、同じ日に、最近亡くなったイヴリー・ギトリスの追悼放送を聞きましたが、ビブラートを感じさせる演奏ではありませんでした。演奏の動作を見れば盛んにビブラートを使っている様子が分かりますが、耳障りな瞬間は無いのです。雲泥の差でした。気を付けて動作を見ていると、ビブラートを使わない時間が4割くらいあるのです。それに比べ、ビブラートが耳障りな演奏は9割くらいの時間をビブラートが占めていました。また時間だけでなく、ビブラートのかけ方も特殊でとても目立つ奏法だったことも耳障りの原因だったのでしょう。
吟のビブラートも耳障りになるかどうかは程度次第です。「程度」と言うのは「深さ」と「速さ」と「占める時間」のことです。
ビブラートは「音程の変化」によるものですから「音程差」が少なければ「浅い」つまり目立たない。「速さ」は音程変化の速さで、速すぎると「ちりめん」といって震え声のようになり目立ってしまう。「占める時間」は文字通りビブラートがかかっている声と、かかっていない声の時間の割合で、簡単に言えば「3割以下」ならあまり気にならないでしょう。
私はビブラートについて過敏な方かも知れません。というのは私が尺八を覚えてきた経緯で、ビブラートをやたらに使わないように教わってきたということが関係するかもしれません。尺八の習い始めでは「首振り3年」は3年経たないうちは首を振らないようにという意味だと教わりました。「首を振る」というのはビブラートをかける時の動作です。尺八の初心者は、とかく息の当て方がずれて音が鳴らなくなってしまうものですからつい首を動かしてなる場所を探ってしまうのです。これが癖になると、常に首を振って演奏する、つまり常にビブラートがかかってしまうという悪い癖がついてしまうのです。高名な尺八奏者にも常にビブラートをかける人がいます。後年、舩川利夫先生に習うようになってからは「ビブラートは表現の為の意味を持って使う」ようにと教わりましたので、ビブラートを聞くと「どういう意味だろう?」と考える癖がついているのです。
意味なく常にビブラートのかかっている声は、表現ではなく声の音色、つまり声質として聞き手に伝わるということです。ビブラートをかけることが癖になってしまうと、ビブラートをかけない声が恥ずかしくて使えないようになってしまいます。こうなると重症と言わなくてはなりません。精神的にビブラートが外せなくなってしまうのです。
声のビブラートは一般的には伴奏とのハーモニー効果を狙う場合が多いのですが、日本の古典音楽ではそのような場合が少ないためにビブラートが無用だったのかも知れません。ビブラートは広い意味で声の装飾と言えますが、日本の伝統的な歌では装飾に「コブシ」を用います。小唄・長唄・民謡・各種浄瑠璃・琵琶歌・吟詠など全て「コブシ」が用いられています。逆の言い方をすれば「コブシ」を用いなければ吟詠も小唄も民謡も成り立たないということです。昭和の時代までは「コブシ」の上手な人が多く、なかには「山盛りのコブシ」を用いる人もいて、「コブシは控えめに」などという注意をされる人もいたくらいだったのですが、平成に入ってからは「コブシ」の苦手な人が多くなり、「ビブラート」を「コブシ」の代わりにする人が増えました。つまり「ビブラート」で「コブシ」のつもりなのです。
「コブシ」を練習することをお勧めします。「コブシ」は素早く回すことが肝腎です。遅いと「コブシ」になりません。かかる時間は一瞬です。「コロッ!」という感じ?とにかく「コブシ」は短いほど良いと思ってください。
基本的に「ビブラート」は吟詠には無用です。
※こちらの質問は『吟と舞』2021年4月号に寄せられたものです