 トップページ
トップページ ×
×
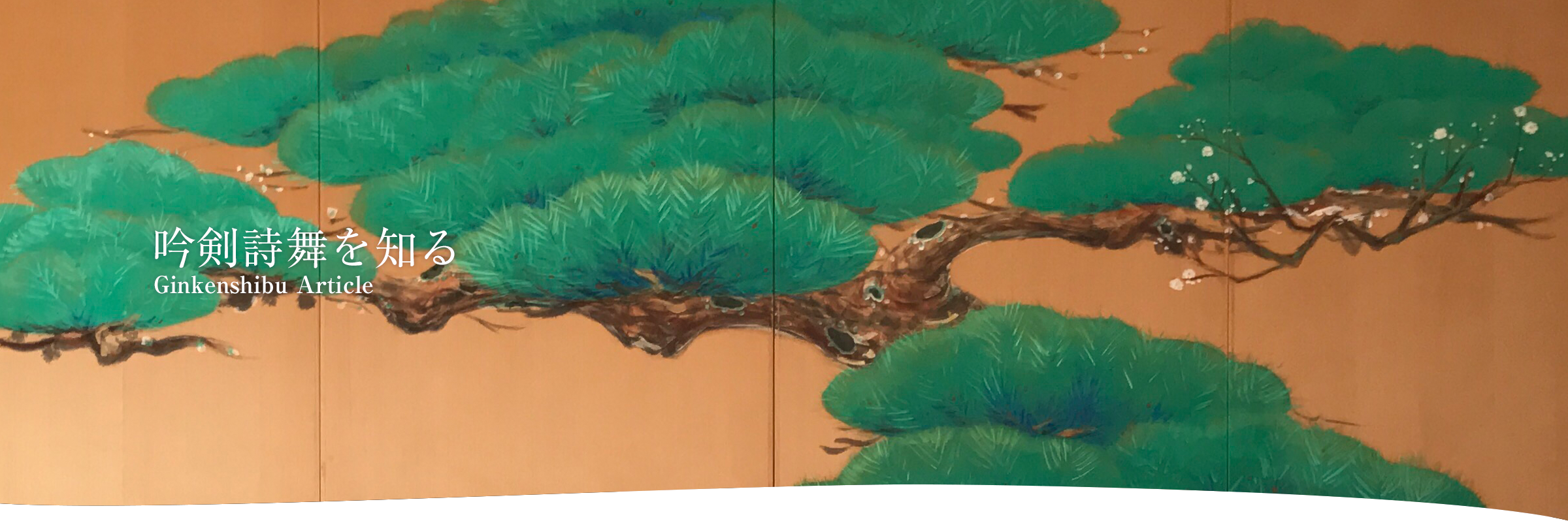

木下犀潭「壇の浦夜泊」
木下犀潭(一八〇五~一八六七)は江戸末期の儒者で、肥後菊池郡の人です。旅の途中、壇の浦に船泊りし、往事を思って詠いました。
壇浦夜泊 壇の浦夜泊
篷窓月落不成眠[篷窓月落ちて眠を成さず]
壇浦春風五夜船[壇の浦の春風五夜の船]
漁笛一聲吹恨去[漁笛一声恨を吹いて去る]
養和陵下水如煙[養和陵下水煙の如し]
〈船の窓に見えていた月は沈んでしまったが、なかなか眠れない。壇の浦で船泊りすると暖かい春風が吹きわたり、もう五更の時分。漁を始めた漁師の笛の音が、安徳天皇はじめ平家一門の恨みをこめるかのように一声響きわたる。見れば、安徳帝のお墓、養和陵の下のあたりの海面は靄のようにけむっている。〉
作者は、平家終焉の壇の浦に船泊りして夜明けまで眠ることができません。一晩中船を包むように吹いていた暖かな春風は、平家の恨みがこもっているようです。春風によって、心の奥にひそんでいた悲しみが少しずつあふれ、月が沈み東の空が明るくなるころには、その悲しみが心いっぱいに広がっています。すると、早暁の静寂をやぶるように漁に出る漁師の笛の音が一声響き渡ります。はっと思い、音のする方を見ると、安徳帝のお墓のあるあたりが靄でけむっています。平易な言葉で淡々と風景を描いて、深い余韻をかもしだしています。
平家の滅亡は『平家物語』によって美しくもはかなく描かれ、人々の涙をさそいます。源平の戦いは、源義経の鵯越の坂落としとして知られる一の谷の戦い(寿永三年、一一八四)、那須与一が扇を射抜いたことでも知られる屋島の戦い(寿永四年、一一八五)、義経の八艘飛びの活躍があった壇の浦の戦いと三つあり、平家の公達が花のように散る描写とともに「あわれ」と「かなしみ」が増してゆきます。
平家は宋(現在の中国)との貿易で繁栄をきわめ、海運の重要なルートである瀬戸内海を支配し、その入り口にあたる関門海峡の彦島(山口県下関市)と、途中の屋島(香川県高松市)に拠点を置いて貿易を独占していました。壇の浦は彦島の目の前にあり、寿永四年三月二四日(一一八五年四月二五日)源義経が彦島に攻め入ると平家軍がそれを阻止しようと奮戦します。が、やがて源氏軍が勢いを得て、わずか八歳の幼帝安徳天皇が入水して戦いは終息します。
入水の時の様子を『平家物語』から少し引用してみましょう。分かりにくい所は〈 〉で口語訳をつけて補足します。
最期を覚悟した母方の祖母・二位殿(二位の尼、平清盛の妻時子)が幼帝を抱き、宝剣を腰にさし神璽を脇にはさみ、船ばたに寄り身を投げようとすると、
「先帝〈安徳天皇〉、今年は八歳、御年のほどよりもおとなしく〈大人びておいでで〉、御髪ゆらゆらと御せな過ぎさせ給ひけり〈お背中の下まで垂れておられた〉。あきれ給へる御様にて〈びっくりなさったご様子で〉、「これはいづちへぞや〈私はどこへ連れて行かれるのか〉」と仰せられければ、御ことばの末をはらざるに〈お言葉も言い終わらぬうちに〉、二位殿、「これは西方浄土へ」とて、〈幼帝とともに〉海にぞ沈み給ひける。あはれなるかなや、無常の春の風、花の姿をさそひたてまつる〈花のような幼帝のお姿を死の底にお誘い申す〉。かなしきかなや、分段の荒波〈生死を分ける荒波〉に竜顔の沈めたてまつる。殿を長生殿と〈御殿を長生殿に〉なぞらへ、門を不老門とことよせしに、十歳にだにも満たせ給はで、雲上の竜下って海底の魚とならせ給ふ。」
漢詩の承句で言う「春風」は右の「無情の春の風」を、転句で言う「漁笛」は「雲上の竜下って海底の魚とならせ給ふ」という件を自ずから思い起こさせます。漢詩の結句、陵のあたりがくもっていると言うのは、涙でくもっていることも表します。
壇の浦の戦いの翌日、漁師たちが網にかかった安徳天皇の遺体を引き上げたという伝説もあります。戦いの一年後、安徳天皇の怨霊を鎮めるため、源頼朝の命によりお堂が建てられました。陵は下関市の阿彌陀寺にあります。
